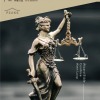技術書典16オフラインイベントにサークル出展しました
目次
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ミジンコに転生したIPUSIRONです😀
技術書典16オフラインイベントにサークル出展しました
2024年5月26日に催された技術書典16オフラインイベントにサークル出展しました。
本記事はその記録となります。
新刊は完売できませんでしたが、目標とする冊数を頒布できました。また既刊も想定以上に売れ、持ち込んだ既刊本(物理本)が売り切れたのはよかったといえます。物理本がなくなった時点でダウンロードカードで対応しました。
イベント当日の会場入り前にやっておいたこと
イベント当日の朝、BOOTHの商品ページを「下書き」から「公開」にし、Xで告知しました。
技術書典16オフラインイベントに来られない人で、新刊の物理本を欲しい人に対応するためです。
サークブース「い11」の様子
持ち物リストに掲載している、いつもの道具を事前に宅急便で送っています。段ボール1個分です。
ポスターはないのでポスタースタンドは用意していません。
頒布物の紹介
今回サークル「ミライ・ハッキング・ラボ」は2人体制だったこと、新刊があることを考慮して、頒布する本を絞りました。
- 『シーザー暗号の解読法』【新刊】
- 『ハッキング・ラボで遊ぶために辞書ファイルを鍛える本』【既刊】
- 『ハッキング・ラボのそだてかた ミジンコでもわかるBadUSB』【既刊】
- 『スタイリッシュ・ハッキング・ラボ』【既刊】
新刊『シーザー暗号の解読法』を改めて紹介します
ゆっくりITちゃんねるさんに紹介していただきました
口頭で頒布物を説明する
見本誌を手に取ってくれたら、相手の様子(読んでいるページ、ページを開くペース、どの程度関心を持っているのかなど)を見て、積極的に口頭で説明しています。
本の紹介アプローチについては、技術書典15の参戦レポートでも書きました。既刊に関しては毎回少しずつ改善していっています。新刊に関しては今回が初なので、手探りで試していくしかありません。
『シーザー暗号の解読法』の紹介例
- シーザー暗号の表紙やキーワードに反応しつつも、通りすがる人に対して「みんな大好きシーザー暗号です」と声をかけました。
- シーザー暗号はどの本にも紹介されるぐらい、大人気で超有名な暗号。
- これからはシーザー暗号の時代がきます。これから流行るかもしれません。
- (冗談めかして)これからはシーザー暗号の時代がきます。
- シーザー暗号は暗号本の最初の数ページだけ紹介されています。読者はさらっとそこを読んでおしまいになってくれますが、それはちょっとかわいそうだと思ったので1冊にしました。
- シーザー暗号の魅力や重要性を認識したので、この1冊に恐縮しました。
- シーザー暗号はシンプルな暗号ですが、本質が詰まっています。シーザー暗号を深く理解すると、他の暗号に見通しがよくなります。たとえば、正しい暗号に出会ったときに、これはシーザー暗号の応用に過ぎないといった判断がすくにできます。
- 今後の人生において古典暗号に出会うことが何度かあるかもでしょう。たとえば、3回あったと仮定しましょう。そのうちの1つが生死をわける状況であり、シーザー暗号を知っていれば助かるというケースもあるかもしれません。
- 暗号には様々なバリエーションの暗号があり、頭がこんがらがります。大げさかもしれませんが、本書を通じてシーザーを理解すれば、古典暗号の半分を理解したことになります。
- まだ世界には未解決暗号文がたくさんあります。それらを解読すれば富と名声を得られます。取材に応じたり、テレビに出たりすれば、さらに収入も得られるでしょう。簡単に元を取れます。
- 古典暗号は一部現代暗号にも通じます。とくに共通暗号はそうです。ビットベースの暗号であれば、ビットの入れ替えであったり、ビットの変換処理が組み合わされています。これは古典暗号の本質といえる、転地と置換そのものです。
- ただし、RSA暗号のように数論ベースの暗号はちょっと状況が違います。
- シーザー暗号の歴史は2000年以上ありますが、シーザー暗号だけで1冊というのは今回が初になります。
『ハッキング・ラボで遊ぶために辞書ファイルを鍛える本』の紹介例
- パスワード解析にはパワードクラッカーというツールを使います。そのツールが高速、高機能であったとしても、同時に使う辞書ファイルが貧弱であると、パスワード解析の成功率が下がります。これを改善するための方法について解説しています。
- 人間がパスワードを設定する際に、何らかの偏りが出ます。たとえば、最後に年号をつけたり、キーボードのキーを1つずつ押していったりなどです。そういった特徴のあるパスワードの候補を自動に生成してくれるツールも紹介しています。
- パスキーが徐々に登場していますが、まだパスワード認証は残り続けます。
- 完全にパスキーが普及した時期になったとしても、人間が扱うシステムを運用するわけであり、セキュリティにおける人間の心理学を知っておくのは無駄ではありません。
『ハッキング・ラボのそだてかた ミジンコでもわかるBadUSB』の紹介例
- (BadUSBの実物を見せながら)BadUSBを知っていますか?
- ⇒NOなら
- 一連のキー入力を実現するスクリプトをこれに入れておいて、パソコンに挿すと自動でキー入力を実行してくれます。何が嬉しいかというと、たとえばWindowsであれば、Winキー押し"cmd"を入力してエンターで、コマンドプロンプトが表示されます。コマンドを入力してエンターを押せば、コマンドが実行されます。そのコマンドが、外部に接続するようなネットワークコマンドであれば、外部とセッションを張り遠隔操作ができるようになります。
- キーボードとして認識されるので、ドライバー不要。アンチウイルスにも検出できません。
- OSにも依存しません。
- このBadUSBはもっともシンプルなものですが、最近のBadUSBは進化しています。無線で接続して、キーストロークを流すタイミングを自由に制御できます。また、複数のスクリプトを内蔵しておき、状況に合わせてスクリプトを切り替えることもできます。たとえば、ターゲットのOSによって異なるスクリプトを用意することもできるわけです。
- ⇒YESなら
- 海外にもBadUSBの文献はありますが、英語配列のキーボードが前提として解説されています。日本人をターゲットにするなら、日本語キーボードが接続されており、BadUSBも日本語キーボードとして振る舞う必要があります。この本にはこうした日本独自の話も書かれています。
今回の課題点
・新刊の見本誌を2冊用意したが、もう少し増やしたほうがよい。
従来どおり、基本的には新刊の見本誌を渡し、余っていなければ既刊の見本誌を渡すという戦法を採用していました。ほとんどのケースではこれで問題ありませんが、まれに新刊の見本誌のみを目的とする人がいて、他の人が読み終わるのを待つという状況が数回ありました。今回の技術書典オフラインイベントの来場者2,600名ぐらいであり、それで待ち状態の人が出てきたということは、今後のイベントを考慮すると「新刊の」見本誌に関しては4冊に増やしたほうがよさそうです。
ただし、新刊の見本誌を増やせば、既刊の見本誌が見る人が減るわけで、既刊が売れなくなる可能性があります。
・新刊『シーザー暗号の解読法』は表紙とタイトルで、通りかかる人の関心を引けました。さらに関心を惹くために、実物があるとなおよかったと実感しています。私自身、他サークルを回った際に何らかの展示物があると目を惹かれました。
今作の巻末付録にはペーパー暗号円盤を載せていましたので、実物を用意するのはそれほど手間ではなかったわけです。それにもかかわらず用意していなかったのは、展示品の重要性を認識していなかったのが最大の原因です。
・今後値札カードを簡略化するか検討する。
買う人は基本的に見本誌を見ているわけで、見本誌の表紙に値段を貼っておいたほうが親切です。
「表紙に値段を貼る」かつ「値札カードを置く」のであれば、もっとも親切だし、売る側も間違った値段を提示しなくて済みます。
一方、完全に値札カードをなくせば、新刊のたびに値札カードを事前に準備する手間とコストがなくなります。机上もその分すっきりします。
どちらを選択するかは要検討といえます。
陳列が上手な他サークルを参考にするのもよいでしょう。他サークルを周っている暇がなかったので(1冊でも多く売るためにぎりぎりまで粘って売っていたので)、次回は周囲も観察したいと思います。
・「裏表紙に本の紹介文を載せる or ブックカバーをつけてから裏表紙側に本の紹介文を載せる」という戦法を検討したが、採用しない。
この戦法が有効なのは、見本誌をひっくり返しておくだけで紹介文を提示できることです。同じ表紙の本が並んでいるより、いろいろな表紙(実際には裏表紙もある)が並んでいると印象づけられれば、通りすがりの人の目を惹く確率が上がります。
我々のサークルの場合は、興味がありそう、サークルブース前の人には基本的に見本誌を手渡すので、この戦法はあまり有効でなさそうです。
逆にサークルブースに人がきても、座って様子見をするようなサークルであれば、この戦法は有効でしょう。
・商業誌を説明の補助として用意していたが、こちらに食いつく人が数名いた。
頒布物とはまったく関係のない商業誌を持ち込むのは、ルール的にOKかは不明です。関係するものであれば、私はポスターみたいな存在だと勝手に思っていますが、本当のところはどうかは運営スタッフに確認してください(サークルブースの設営時にスタッフが回ってくるのでそのとき聞くのでもよいでしょう。ダメなら出さなければよいだけ)。
頒布・展示の禁止物については、こちらに載っています。
頒布物(売り物)ではない商業誌を展示することの利点は結構あります。
「売りたい同人誌の紹介に活用できる」「同人誌を売りつつ、商業誌を宣伝でき、著者をアピールできる」「商業誌を出している→同人誌の出来や品質の信頼性が高まる→購入の可能性大」「たとえば『ハッキング・ラボのつくりかた 完全版』を置けば、分厚くて目立つし、「この本を持っています」「(知らない人からは)この本何ですか?」と話が盛り上がる→心理学的に親密度が高まれば結同人誌を買ってくれる可能性が高まる」「同人誌の内容だけでは興味を惹かれないが、著者に惹かれた→記念で買う人が少数ながらいる」
しかし、サークルメンバーの人数によっては安易に採用しないほうが無難です。
1人サークルであれば問題ありませんが、当サークルのように複数人のメンバーがいる場合はよく検討しなければなりません。1人だけが目立つことになりかねず、他メンバーとの軋轢を生む恐れがあります。
当サークルは今回たまたま2人体制だったこと、自分からではなく他メンバーから商業誌を持ってくることを提案してくれたので、たまたま問題ありませんでした。
もし多人数サークルでこの手法をやるのであれば、十分に話し合っておきましょう。たとえば、毎回この戦法を発動するのではなく、新刊のときだけ許可するなどのようにするわけです。話し合いの場では全員納得したとしても、イベントを通じてやっぱり納得いかないと心変わりする可能性もあります。
・イベント前後はフォロー返しをしてもらえるチャンスなので、積極的にフォローする。
これは実践済みだが、もう少し有効な方法を検討したいところです。
ただしやりすぎるとXからボットやスパムの誤認定されてロックされる恐れがあるので、注意してください。
・多くの人がイベント直後に戦利品を投稿しますが、次の日、あるいは自宅に荷物が届いてから報告する人も若干名います。そういった事情を考慮に入れて、数日間にわたってXにて「技術書典」[1] … Continue reading「戦利品」で検索したほうがよさそうです。
戦利品報告をいいね、当サークルの本があればリポストするようにします(これはこれまでどおりのムーブ)。
オフラインイベントが終わっても、オンラインマーケットは継続しており、オンラインの終了間際に本を注文する人もいます。ただし、オンラインマーケットでの購入はシステムの仕様上、1冊ごと決済しなければなりません。決済を完了すると、最後にXに共有することを促されます。それに応じて共有された場合、「戦利品」と表現する人は少ないでしょう。つまり、オンラインマーケットの購入者を探すには、シンプルに本のタイトルで検索すれば十分です。
技術書典16オフラインイベント後
私の戦利品【おまけ】
その他の本に関しては、自宅に帰ったらオンラインマーケットでじっくりと探したいと思います。
References
| ↑1 | 「#技術書典」で検索したいところですが、ハッシュタグを使っていない人もちらほらといて、そういった人を取りこぼさないためにはあえてシャープ記号を外すのが有効です。外しておけば、どちらも検索対象になるからです。 |
|---|