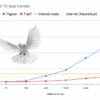伝書鳩による通信
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ミジンコに転生したIPUSIRONです😀
鳩通信とは
無線通信が普及する以前、軍事における重要な通信手段のひとつが伝書鳩でした。
鳩は遠く離れたところからでも自分の巣に帰ろうとする帰巣本能が強い生き物です。つまり、遠隔地との連絡手段として利用できたのです。このとき使われる鳩を伝書鳩と呼び、特に軍事用の鳩を軍鳩(軍用鳩)と呼ばれます。そして、鳩による通信を鳩通信と呼ぶことにします。
伝書鳩の歴史
古代から中世
伝書鳩の利用は古く、紀元前1200年頃の古代エジプトにまで遡ります。当時、ナイル川の氾濫状況を伝達する手段として鳩が使われていました。
ローマ時代には、皇帝ユリウス・シーザーがガリア戦争や内戦において伝書鳩を活用しました。特に包囲された都市との通信においては伝書鳩が重宝されました。地上の伝令は敵の妨害にあいやすいですが、鳩ならば空を飛んで情報を伝えられるためです。
第一次世界大戦
第一次世界大戦では、伝書鳩が前線部隊の重要な通信手段として活躍しました。塹壕戦の影響で電話や電信の回線が砲撃で切断されることが多く、当時の無線通信も不安定だったため、伝書鳩のほうがより信頼できる情報伝達手段とされていました。
第二次世界大戦
第二次世界大戦でも50万羽以上の伝書鳩が活躍しました。特にイギリス軍は陸海空軍で伝書鳩を積極的に導入し、非常時の通信手段として備えていました。
また、イギリスの諜報機関はコロンバ作戦として、ドイツ占領下のフランスへパラシュートをつけた伝書鳩を投下しました。鳩は現地のスパイやレジスタンスが回収し、重要な情報をイギリス本土へ送る手段として活用されました。
現代
電子通信技術の発展により、軍事用途としての伝書鳩の役割はほぼ終えました。
しかしながら、非常時の通信手段としての活用や、レース競技としての訓練は今も続けられています。その歴史的背景と有用性は、現在も語り継がれています。
鳩通信の特徴
鳩通信にはメリットとデメリットがあります。ここでは、その代表的なものを示します。
メリット
遠距離通信が可能
伝書鳩は数百km以上離れた地点からでも帰巣できます。
妨害されにくい
電波妨害や物理的な通信遮断の影響を受けにくい特徴があります。
物理的な物体を運べる
大容量かつ小型の記憶媒体を運ばせれば、データの高速通信を実現できます。
独立した通信手段
無線通信や有線通信が使えない環境でも機能します。
秘匿性が高い
通信していること自体が敵に察知されにくいといえます。特に現代であればなおさらです。
デメリット
一羽だけでは一方向通信に限定される
放した鳩は巣にしか戻れません。つまり、一匹の鳩では双方向の通信ができません。
通信の信頼性が低い
伝書鳩が必ずしも戻ってくるとは限りません。悪天候や天敵の存在により帰還率が下がります。
敵の鳩通信を妨げるために、ドイツ軍は猛禽類(タカやハヤブサなど)を放ったという話がありますが、公的な記録はなく、逸話の域を出ないとされています。ただし、軍鳩を使ったスパイ活動に対する取り締まりや、軍鳩を捕獲・撃墜した者に奨励金を出す制度は実施されていました。
複数の伝書鳩に同じ情報を持たせれば信頼性を向上できるが、それでも完璧とはいえません。
インターネット通信は、鳩通信に大容量データの通信速度で負けることはあっても、確実にデータを転送できます。ネットワークの通信で使われているプロトコル(通信規則)には誤り訂正や再送といった、データの欠落を防ぐ機能が備わっているからです。
コストがかかる
帰巣本能を活かすための事前訓練、餌など飼育のための日々のコストなどを考慮しなければなりません。
運用終了後の管理が困難
役目を終えた鳩の処遇を考慮しなければなりません。
なお、靖国神社(東京都千代田区)の境内には、兵士と共に戦った軍馬・軍犬・軍鳩のための慰霊像があります。
他にも、全国各地に軍鳩のための慰霊碑や供養塔が存在します。